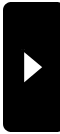【夏】馬堤溜の変化【冬】
すっかり寒くなりました。
季節が夏から冬に変わるにつれ、探検の殿堂横にある馬堤溜(うまづつみだめ)も姿を変えていることに気づきました。
これが夏の馬堤溜。

水面を水草が埋め尽くしています。タロジロもまるで草原にいるよう。
これは冬の馬堤溜。

水草が影も形もありません。美しい水面。
私が探検の殿堂で働き始めた時は水草なんて一つも見当たらなかったので、季節が変わるにつれてどんどん増殖していく水草に驚きました。私より長くここで働いているハミガキさん曰く、「毎年そう!夏になると水草があがってきて、冬になると沈む!!」とか。
なので私は、きっと光合成とかそういう関係で夏になると太陽の光に反応して池の底から水草が浮き上がってくるんだと思ってたんです。
しかしその後それは間違いであることが分かりました…。正しくは
(誤り)夏になると水面に浮き上がってくる。
(正解)春になると水底に沈んだ種が発芽して成長。冬になると枯れる。
そして馬堤溜の湖面に繁殖しているのは、ヒシとよばれる水草だと(私の中で)判明。

秋口ごろの馬堤溜。手前にたくさんの枯れたヒシがあります。このころになると葉は枯れはてて、茎だけが残っています。

枯れたヒシは、そのまま水底に沈んで湖の養分になるのでしょう。種が冬を越すんですね。
ヒシのように、種から発芽して一年以内に生長し、花を咲かせたり実をつけた後は種を残して枯れてしまう植物を「一年草(いちねんそう)」というそうです。へぇ~~。
ちなみに
私は食べたことはありませんが、ヒシの種はデンプン質が豊富に含まれており、茹でたりすると美味しいらしいです。昔の子どもたちにとっては、ヒシの種は美味しいおやつ。危険をかえりみず、種を採ろうとギリギリまで身を乗り出してそのまま……ということもあったとかなかったとか
身近な自然も調べてみないと分からないものですね。
しばらくは馬堤溜の綺麗な水面をお楽しみください。
季節が夏から冬に変わるにつれ、探検の殿堂横にある馬堤溜(うまづつみだめ)も姿を変えていることに気づきました。
これが夏の馬堤溜。
水面を水草が埋め尽くしています。タロジロもまるで草原にいるよう。
これは冬の馬堤溜。
水草が影も形もありません。美しい水面。
私が探検の殿堂で働き始めた時は水草なんて一つも見当たらなかったので、季節が変わるにつれてどんどん増殖していく水草に驚きました。私より長くここで働いているハミガキさん曰く、「毎年そう!夏になると水草があがってきて、冬になると沈む!!」とか。
なので私は、きっと光合成とかそういう関係で夏になると太陽の光に反応して池の底から水草が浮き上がってくるんだと思ってたんです。
しかしその後それは間違いであることが分かりました…。正しくは
(誤り)夏になると水面に浮き上がってくる。
(正解)春になると水底に沈んだ種が発芽して成長。冬になると枯れる。
そして馬堤溜の湖面に繁殖しているのは、ヒシとよばれる水草だと(私の中で)判明。
秋口ごろの馬堤溜。手前にたくさんの枯れたヒシがあります。このころになると葉は枯れはてて、茎だけが残っています。
枯れたヒシは、そのまま水底に沈んで湖の養分になるのでしょう。種が冬を越すんですね。
ヒシのように、種から発芽して一年以内に生長し、花を咲かせたり実をつけた後は種を残して枯れてしまう植物を「一年草(いちねんそう)」というそうです。へぇ~~。
ちなみに
私は食べたことはありませんが、ヒシの種はデンプン質が豊富に含まれており、茹でたりすると美味しいらしいです。昔の子どもたちにとっては、ヒシの種は美味しいおやつ。危険をかえりみず、種を採ろうとギリギリまで身を乗り出してそのまま……ということもあったとかなかったとか

身近な自然も調べてみないと分からないものですね。
しばらくは馬堤溜の綺麗な水面をお楽しみください。