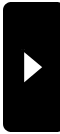ロボカップジュニア東近江ノード大会(オープン・ライトウェイト)
本日、探検の殿堂でロボカップジュニアの東近江ノード大会(オープンとライトウェイト)が開催されました!
ロボカップジュニアの公式サイトはこちら↓
http://www.robocupjunior.jp/index.html
ロボカップジュニアとは、子ども達の好奇心や探求心を引き出し挑戦できる3種類の競技テーマ(サッカーリーグ、レスキューリーグ、OnStageリーグ)があり、誰でも参加できる大会です。ロボットの設計製作を通じて、基礎的な能力だけでなく、協調性や他人と協力することの大切さを学ぶことを目的としています。全国各地でノード大会(地区予選)が行われ、そこで勝ち抜いたチームがブロック大会へと進みます。
というわけで、探検の殿堂で東近江ノード大会・サッカーリーグが行われたのです。
サッカーリーグでは、使用するロボットの重さによってクラスが分かれています。色々な部品や機能が増えるほど、ロボットは強力になっていくので、重量でクラスを分けているようです)
受付を死守していた関係で途中からになったのですがオープン・ライトウェイトの東近江ノード大会の様子をご紹介したいと思います。

絶賛試合中のところをお邪魔しました。こちらはライトウェイト級の試合。競技に使うロボットは自軍2機、相手軍2機の計4機。2人で1チームです。

オープンとライトウェイトでは、写真の通り背の高いサッカーコートを使います。サッカーリーグはクラス別で使うコートが異なり、それとともにルールも変わってくるそうです。コートに書かれている白い白線からロボットやボールが飛び出したら、審判がボールを白線内部に戻したりしていました。
※私は人間がやるサッカースすらちゃんとルールを知っているとは言い難い人間です。

試合が始まる直前まで、真剣な表情でロボットを調整する子どもたち。

他の子どもたちも、ギリギリまでロボットを調整しています。
何のトラブルもなく試合を迎えられたら良いのですが、そうは問屋が卸さない。
いくつかのチームはロボット(のセンサー?)が上手く動かなくなったりして、何とか動かそうと焦りながらも色々試したり努力していました。

オープンの試合。オープンも二人一組ですが、使うロボットは1機のようです。サッカーのボールも、赤い光を出す球体ではなく、オレンジ色の普通のボールを使っています。余談ですが、↑の二人は、初めてロボットを扱う子どもたちがプログラミングを学ぶ「科学探検隊ココロボ」で、みんなのお兄さん役としてサポートに入ってくれていた子たちです。

なんのかんのとありつつも、試合は終了。閉会式を迎えました。
みんな頑張りました
大会である以上、勝った負けたがあるわけです。
参加者の一人に大会の感想を聞いてみたら「ぼろ負けやった…」と一言。
しかし、大会を見ていた私はこう思いました。
「勝ち負けよりも、迫りくる時間内に、なんとか課題を解決する経験を積んでいるのが素晴らしい!」って
時間がない!焦る!どうしよう!!という強いストレスがかかった状況で、諦めずに本来の能力を発揮することは非常に難しいことだと思います。
傍から見ていると、子どもたちのロボットそのものよりも、子どもたちがどんなふうに問題や精神的な焦りに対処しているかの方に私は注目してしまったのでした。
(勝ち負けも大事だよ~~と言われそうですが汗)
ロボカップジュニアはそういう訓練や経験を積む場としても優れているのかもしれません。
みんな、お疲れさま!
12月2日には探検の殿堂で、ビギナーズの東近江ノード大会も行われます!
ロボカップジュニアの公式サイトはこちら↓
http://www.robocupjunior.jp/index.html
ロボカップジュニアとは、子ども達の好奇心や探求心を引き出し挑戦できる3種類の競技テーマ(サッカーリーグ、レスキューリーグ、OnStageリーグ)があり、誰でも参加できる大会です。ロボットの設計製作を通じて、基礎的な能力だけでなく、協調性や他人と協力することの大切さを学ぶことを目的としています。全国各地でノード大会(地区予選)が行われ、そこで勝ち抜いたチームがブロック大会へと進みます。
というわけで、探検の殿堂で東近江ノード大会・サッカーリーグが行われたのです。
サッカーリーグでは、使用するロボットの重さによってクラスが分かれています。色々な部品や機能が増えるほど、ロボットは強力になっていくので、重量でクラスを分けているようです)
受付を死守していた関係で途中からになったのですがオープン・ライトウェイトの東近江ノード大会の様子をご紹介したいと思います。

絶賛試合中のところをお邪魔しました。こちらはライトウェイト級の試合。競技に使うロボットは自軍2機、相手軍2機の計4機。2人で1チームです。

オープンとライトウェイトでは、写真の通り背の高いサッカーコートを使います。サッカーリーグはクラス別で使うコートが異なり、それとともにルールも変わってくるそうです。コートに書かれている白い白線からロボットやボールが飛び出したら、審判がボールを白線内部に戻したりしていました。
※私は人間がやるサッカースすらちゃんとルールを知っているとは言い難い人間です。

試合が始まる直前まで、真剣な表情でロボットを調整する子どもたち。

他の子どもたちも、ギリギリまでロボットを調整しています。
何のトラブルもなく試合を迎えられたら良いのですが、そうは問屋が卸さない。
いくつかのチームはロボット(のセンサー?)が上手く動かなくなったりして、何とか動かそうと焦りながらも色々試したり努力していました。

オープンの試合。オープンも二人一組ですが、使うロボットは1機のようです。サッカーのボールも、赤い光を出す球体ではなく、オレンジ色の普通のボールを使っています。余談ですが、↑の二人は、初めてロボットを扱う子どもたちがプログラミングを学ぶ「科学探検隊ココロボ」で、みんなのお兄さん役としてサポートに入ってくれていた子たちです。

なんのかんのとありつつも、試合は終了。閉会式を迎えました。
みんな頑張りました
大会である以上、勝った負けたがあるわけです。
参加者の一人に大会の感想を聞いてみたら「ぼろ負けやった…」と一言。
しかし、大会を見ていた私はこう思いました。
「勝ち負けよりも、迫りくる時間内に、なんとか課題を解決する経験を積んでいるのが素晴らしい!」って

時間がない!焦る!どうしよう!!という強いストレスがかかった状況で、諦めずに本来の能力を発揮することは非常に難しいことだと思います。
傍から見ていると、子どもたちのロボットそのものよりも、子どもたちがどんなふうに問題や精神的な焦りに対処しているかの方に私は注目してしまったのでした。
(勝ち負けも大事だよ~~と言われそうですが汗)
ロボカップジュニアはそういう訓練や経験を積む場としても優れているのかもしれません。
みんな、お疲れさま!
12月2日には探検の殿堂で、ビギナーズの東近江ノード大会も行われます!